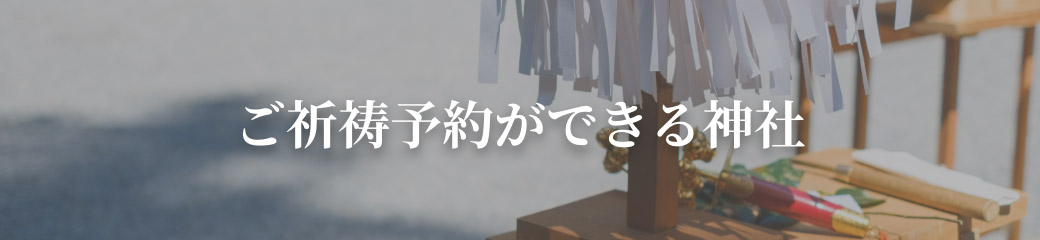公式
神鳥前川神社
しととまえかわじんじゃ
横浜市青葉区しらとり台 田園都市線 田奈駅徒歩7分、青葉台駅徒歩15分 (JR線)、十日市場駅 徒歩 20分
田奈 青葉台総鎮守 神鳥前川神社
- 基本情報
- 写真ギャラリー(6)
- お祭り・行事
- アクセス
基本情報
| 神社御名称 | 神鳥前川神社 |
|---|---|
| 鎮座地 (住所) | 〒227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 |
| アクセス | 田園都市線 田奈駅徒歩7分、青葉台駅徒歩15分 (JR線)、十日市場駅 徒歩 20分 |
| 駐車場 | あり (表参道 4台・裏参道 8台・境内上 6台 ※神社駐車場に限りがありますので、七五三等の混雑時は最寄りの田奈駅(徒歩7分)周辺の有料駐車場をお使いになられることをお勧め致します。) |
| 電話番号 | 電話で予約問合わせ 045-983-0707 ※お問合わせの際はMy神社を見たとお伝えになるとスムーズです。 |
| 公式サイト | http://www.shitodomaekawa.com/ |
| 受付時間 | 09:00 〜 16:00 |
神社詳細情報
| ・沿革 天正十年(1582年)火災により社殿が焼失し、当時この地を治めていた上杉景虎(謙信の子)が社殿を新しく建立寄進し、かつ毎年春秋の上納金より三貫文を社料として免租するという内容の古文書が残されて居ります。 また、現在八坂神社、 稲荷神社としてお祀りされている旧本殿はその後再建されたものであり、拝殿及び覆殿は文化九年(1812年)当時 の地頭岡本玄治法眼を始め橋本、船橋宋迪、朝岡、星合鍋五郎等の寄進で再建せしものであると棟札に記されて居ります。 明治43年12月23日、当所曲り坂7439番地(現・しらとり台第三公園付近)に祀られていた 無格社・神明社祭神伊邪那岐命(イザナギノミコト)・伊邪那美命(イザナミノミコト)を合祀するに際し、拝殿が手狭になるため、 本殿を拝殿と別棟の覆殿下に収め、同時に玉垣・舞殿・社務所等の改修を計画、着工致しましたが覆殿の造営が予定通りには完成せずに終わり、 その後昭和29年に、茅葺屋根を腐食防止のため金葺にする工事が施されました。 その後昭和63年5月に現在の神社殿の建設・御遷座が行われ現在に至って居ります。 ・神鳥(しとど)考 全国には日本武尊を御祭神にお祀りする神社は数多く見られ、鷲(オオトリ)神社や白鳥神社など鳥の付く社名が多く見受けられます。これは由緒の中でも触れられたように日本武尊が逝去されると、白い鳥に姿を変え、飛び立たれたという故事によるものです。 いつの頃から当社の社号に「神鳥」の文字が付くようになったのかは定かではありませんが、鷲や白鳥と同様、霊鳥を意味する「神鳥」の文字が当てられました。 さて、古くから霊鳥とされる鳥に実在する「之止止」(鵐シトト)と言う鳥がいるのですが、背に青い筋があることから「アオヒト」とも呼ばれ、これに「一青」の字をあてるようになりました。北陸地方の地名や姓で「一青」(ヒトト)というものや、栃木県小山市には神鳥谷(ヒトトノヤ)という地名もあります。また、この『之止止』は霊鳥であることから、神鳥や巫鳥(ミコドリ)の二字が当てられるようになりますが、後にはこれらを合わせて「鵐」と書き「シトド」と読むようになりました。 よく知られる名称では、厚紙に穴をあけたときに、その周りを装飾・補強をする金具を鳩の目に似ていることから「鳩目」と言うものがあります。同様に、木製品や金属製品に穴をあけたときに用いる金具は「鵐目(シトドメ)」と呼ばれています。 ・日本一の大幟 現在社殿の左右に亭々と聳える大幟は天保10年(1839年)秋、 当時、恩田千石と言われた土志田半兵衛なる人の旺んな時に出来たものです。 その竿の長さは11間半(約11.7メートル)、幟の巾は約6尺(約1.8メートル)で、 別の言い方をすれば5巾もあり、普通の大幟が3巾ないしは4巾ということを考えると、 7間半にも及ぶその長さと併せ、その大きさが伺い知れるでしょう。 総欅の駒寄の中に高さ8尺にも余る幟竿が立ち、その冠頭を飾る雌雄の龍をかたどる彫刻の見事さ、その豪快さは他に類がなく(現在は拝殿に安置されている。)、当時の漢学者石川武陽の筆による社号の文字のすばらしさとともに「関東一」あるいは「日本一」と語り継がれてきました。 また、この見事さ故に、この幟が立つと「龍が水を呑みに川へ降りるから必ず雨が降る」と云う言い伝えもあります。 現在、社殿裏側の小屋に幟竿二本が保管されていますが、往時は石段下の県道に立てていたもので、 様変わりした今日ではとても立てるべき場所もないという理由から、高さを同じ規模にしたアルミ製の幟竿に替えて、前述のように社殿前に移設されました。 | |
| ご由緒 当社は文治三年(1187年)五月、武蔵国桝杉城主・稲毛三郎重成により創建されました。重成は敬神の念篤く、所領稲毛に稲荷社を建立すると共に霊的な夢のお告げを受け、武神日本武尊(ヤマトタケルノミコト)及びその妃弟橘比売命(オトタチバナヒメノミコト)を御祭神としてこの地に祠を建て白鳥前川神社と名づけたと言い伝えられて居ます。 白鳥というのは御祭神日本武尊が伊勢の国煩野(ノボノ)にて逝去の際、神霊化され白鳥になられたという故事により、また前川とは神域の真下を鶴見川支流の恩田川が流れおり、弟橘比売命(オトタチバナヒメノミコト)の入水の故事に重ね合わせて名付けられたものです。それがいつの頃よりか白鳥が転じて神鳥と書くようになり、これを「シトド」又は「シトトリ」と読むようになり、今日に至って居ります。 境内周辺の鬱蒼とした樹木や社前を流れる清らかにして盛大な川の流れは畏敬の念を与え、遠近にその名を知られるようになりました。 以来、武門武家の崇敬が厚く、現在当社に面する田奈町の小字「馬場」という地名は、その寄進による馬場の跡だと伝えられて居ります。 | |
| 御祭神 | 伊邪那岐命(イザナギノミコト)・伊邪那美命(イザナmノミコト)・仲睦まじいことで有名な日本武尊(ヤマトタケルノミコト)・弟橘比売命(オトタチバナヒメノミコト)夫婦二組の神様をお祀りしています。 |
|---|---|
| 創建 | 1187年 |
| ご利益 | 恋愛成就・縁結び 病気平癒 交通安全 勝負運 |
| お守り・おみくじ | やっている |
| 御朱印 | やっている |
| 供養・お焚き上げ | やっている |
| 祈願・お祓い | 七五三 成人式 厄払い 安産祈願 初宮詣 結婚式 出張祭典(地鎮祭他) |
| 各種初穂料(ご祈祷料) | 安産祈願: 8,000円 〜 七五三: 10,000円 〜 厄払い: 5,000円 〜 |
続きを表示